河川流域マネジメント工学
流域と都市の問題を解決するためには、環境変化の現状と要因分析をもとに、社会・経済活動と自然力・自然環境が織りなす複雑な相互関係を常に射程におきながら、人と自然にやさしい、持続可能な流域・都市システムを構築していく必要があります。
本研究室は、流域及び都市における人と自然の共生や持続可能な発展を支えることを目的として、
- 河川流と河川地形変化の数値シミュレーション法とその実際的な応用
- 湖沼などの水域環境予測モデル
- 都市雨水排水系と地下水の水理解析
- 流域水動態の分析とモデリング
- 水問題解決のための河川と流域の効果的なマネジメント
などに関する研究をおこなっています。
教員
市川 温 ( Yutaka ICHIKAWA )

教授(工学研究科)
研究テーマ
流域に降った雨水はさまざまな経路を通じて流動しています。都市域に降った雨のように極めて短い時間で流れ出てくる水もあれば、地下水のように非常に長い年月をかけて流動する水もあります。このように、流域内の非常に多様な水の動きを分析し理解すること、そしてその結果に基づいて、流域水動態を予測するための数理モデルを開発することを研究テーマとしています。
また、洪水・渇水などのさまざまな水問題は、人間社会と水循環の交わるところで生じます。水の恩恵を受けつつ、できるだけ水に伴う問題を防止・軽減するためには、水循環とうまく折り合いをつけながら人間社会を営む必要があります。このようなことから、河川と流域の効果的なマネジメントについても研究テーマとしています。
連絡先
桂キャンパス C-1 3号棟 2階265号室
TEL: 075-383-3266
FAX: 075-383-3271
E-mail: ichikawa.yutaka.5w![]() kyoto-u.ac.jp
kyoto-u.ac.jp
研究テーマ・開発紹介
河川流と河床・河道変動の数値シミュレーション法の開発と流域計画への応用
河川の流れと河床・河道変動(川の地形変化)の予測法についての研究は、洪水防御のための洪水時の水位予測、川の湾曲部や構造物周辺の洗掘深(川底が掘れる深さ)の予測、安定した河道の設計などのために必要であったため、水工学の主要な分野として古くから精力的に研究がおこなわれてきました。
最近では、コンピュータのハード的及びソフト的な目覚しい進歩を反映して、数値シミュレーションによる予測法の研究が主流で、実用的な平面2次元モデルから3次元複雑乱流解析を伴う河床地形の予測モデルまで、活発な研究がおこなわれている分野です。
図-1は、砂地に溝を掘り水を流した後の地形変化のシミュレーション結果を図示したものです。最初交互に砂州が形成され、そのために流れが蛇行するとともに左右岸を侵食し、流路の蛇行が進行する様子が分かります。
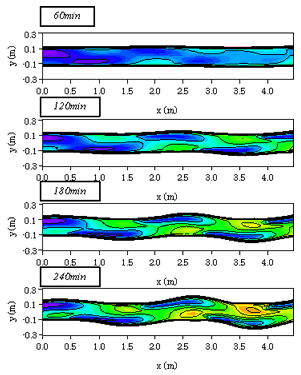
図-1 川の蛇行発生の数値シミュレーション
(砂に溝を掘り水を流した後の地形変化)
図-2は、砂堆と呼ばれる河床波の発生・発達過程のシミュレーション結果を示したものです。
上流側で発生した微小擾乱が時間の経過とともに増幅していき、砂堆が発達していく様子が分かります。また、砂堆の発達にともなって、流れの抵抗(水深)が増加していることが確認できます。

図-2 砂堆の発生・発達過程と流れの抵抗の増加の数値解析結果
都市社会流体工学の構築
都市再生を支える技術を流体工学の観点から見直し、関連があまりないように見える個別の要素解析技術を横断的に検討することで、都市社会再生を目的とする流体工学を構築しようとしています。
都市社会工学専攻や他専攻の所属教官で研究グループを構成し、研究を推進しようとしている分野です。たとえば、下記は具体的テーマの一つである「親水都市デザイン」の説明です。
親水都市デザインの説明
都市の潜在能力を発展させアメニティの質を向上させるために、水の効用を多様な視点からとらえた親水都市デザインが必要です。たとえば、次のような視点が考えられています。
- 環境防災・都市水害も考慮した水供給・排水系の構築
- 都市内水辺ビオトープ・ネットワークの創生と保全
- 親水空間の景観やアメニティ向上のための水の造形デザイン
図-3は親水アメニティ空間創出のために、多数のサイフォンなどを使用した複雑管水路系を用いた水時計の例です。

図-3 ベルナール・ジトン氏作の水時計(西武百貨店八尾店)
湖沼などの水域環境予測モデルの開発
湖沼など水域の環境を把握・理解し予測する研究をおこなっています。
図-4は、深いところで水深が100メートル程度ある琵琶湖北湖の溶存酸素鉛直分布の季節変化を示しています。左がシミュレーションで右が観測結果(滋賀県衛環センター公開データ)です。
近年、湖底での溶存酸素の低下が懸念され、地球温暖化の影響ではないかとの議論がありますが、基礎的な解析を通じて全体的な物質循環の機構を把握し客観的に議論することが必要なようです。
シミュレーション結果には、夏から秋にかけて水温成層上部に極小部が現れること、1月に底層の値がかなり小さくなること、2月、3月には水温成層消滅による大きな鉛直混合と水表面からの供給によって、溶存酸素が底層にまで供給される様子が再現されています。
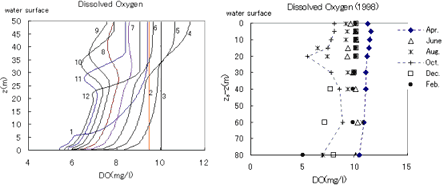
図-4 琵琶湖北湖の溶在酸素鉛直分布の季節変化に関するシミュレーション
